タワーマンションと低層マンションでは、規模や立地など住み心地や資産性にかかわる特徴が異なります。
そこで本記事では、地上20階建て以上のタワーマンションと、地上5階建て以下の低層マンションを比較し、徹底解説します。
住み心地
生活利便性
2015年1月~2021年11月に販売された新築マンションデータ(不動産経済研究所調べ)によると、総戸数200戸以上が全体の7割を占めるタワーマンションに対し、低層マンションは50戸未満が8割超となっています。
基本的にタワーマンションは大規模物件が中心で、低層マンションは小規模物件が中心という傾向がうかがえます。敷地にゆとりがあり、コスト面でもスケールメリットを活かしやすい大規模物件は、共用施設の数や種類が豊富です。コロナ禍で、テレワーク用スペースを設ける大規模物件が増えましたが、これも敷地に余裕があるからこそ、ニーズの変化に応じて柔軟に対応しやすかったという側面があります。
タワーマンションの場合、商業施設やクリニックモール、保育施設などが併設された複合開発物件も多いので、全般的に生活利便性が高い傾向にあります。一方、小規模中心の低層物件は、落ち着いた住環境がメリットとなります。
小規模物件が多い低層マンションの場合、ワンフロアの住戸数が少な目で共用廊下を通る人が限られます。静かな上、セキュリティ面でも安心度が増すのです。また、大規模なタワー物件では、朝の通勤時間帯などにエレベーターが混雑してすぐに乗れないことがあります。低層物件なら混雑度合いは軽減されますし、そもそも階段利用を視野に入れられます。
なお、少数ではありますが、敷地内に複数棟が配置され、低層ながら総戸数では大規模となる物件もあります。このようなケースでは、タワー同様、共用施設も充実していて、住環境・生活利便性ともに高水準という、いいところどりを実現できることもあります。
交通利便性と住環境
立地面で両者を比較すると、2015年1月~2021年11月に販売された新築マンションデータ(不動産経済研究所調べ)によると、低層マンションは最寄駅から徒歩5分以内の物件が約3割である一方、タワーマンションでは約6割を占めています。低層マンションも8割以上は徒歩10分以内だが、より駅近立地を求めるならタワーマンションに軍配が上がります。
タワーマンションの立地は複数路線・複数駅を利用できるケースが多く、最寄駅周辺のにぎわいもひとつの特徴です。立地面でも利便性を重視して開発されている表れでしょう。
一方、低層物件の駅徒歩分数は、タワーマンションに比べてバラつきが見られます。この点については、利便性以外でもセールスポイントになりうる要素があるからだと考えられます。
閑静な住宅街として人気のエリアでは、建物の高さや規模が制限されているケースがあります。こうしたエリア一戸建て分譲すると価格設定が高くなりがちなので、価格を抑えやすいマンションが開発されるわけです。ただし、閑静な半面、最寄駅で利用できるのは1路線各駅停車のみということがあります。商業施設の充実度も、複数路線を使える駅や急行停車駅ほど高くないケースも。それでも公園や学校が近いなど、良質な住環境に価値を見出す人から評価されているのです。
利便性を重視するか、子育てなどに適した落ち着いた環境を重視するかによって、選択するのも一つの指標となります。
資産性
住まいに求める価値の変化
住まいは自身や家族が憩う大切な場所です。かつては、住宅購入は一生に一度とも言われ、自分自身や家族の条件を満たすことが全てと言っても過言ではありませんでした。しかし、都市部においてはライフステージに合わせた住み替え、買い替えなどが当たり前のように行われ、自分や家族の満足だけでなく、社会経済の状況や不動産ニーズの変化などを重視し、投資的な視点を持った住まい選びがスタンダードになっています。
不動産の資産性の指標としては過去の同エリアにおける不動産取引価格や、類似条件を満たした物件のリセールバリューに目が向かいがちですが、リセールバリューはあくまで過去の情報との比較であることは否めません。過去との比較も有益な指標ではあるものの、不動産に限らず、投資という観点でより注視すべきは5年後、10年後の世界。株などの投資と同じく、過去に伸びてきた商品が同様に推移するとは限らない以上、そこに伸び代があるかどうか、伸びる理由を見極められるかどうかが肝となります。
10年後の街の姿を見出せるか
理由もなく価値が上昇するのは単なるバブルですが、明確な理由が見える場合には少なくとも価値が下がりにくい傾向にあります。近年の大きなトレンドとしては、やはり大規模再開発による街の再生が挙げられるでしょう。2020年以降も都心の不動産相場が今現在(2022年2月)上昇傾向にあるのは、現在もなお、各地で街が進化し続けているからといえます。しかし、その再開発ラッシュもこの先10年である程度落ち着くでしょうし、何より現在はたった5年経てば暮らしがガラリと変わるような変化の激しい時代です。新型コロナウイルス収束後にはどのような時代が来るのでしょうか。不動産に住まいであることに加えて価値を見出す方にとってはそうした変化を見据えた上で未来をイメージする力が必要となっていくでしょう。
グローバルな視点を持てるか
そこでポイントとなるのは、国内の相場だけでなく、海外から見て価値があるのか、というグローバルな視点です。例えば、海外に不動産を購入するなら、どのような街の、どのような物件を購入するでしょうか。国外から見ても知名度の高い街で、他に類するものがない象徴的な物件に目を奪われることは至極当然のことだと思います。
これまでの価値観にとらわれず、未来を見据えた価値を掴めるかどうか。そうした視点を持つことで、新たな価値に気づくことでしょう。
まとめ
本記事ではタワーマンションと低層マンションの特長について、解説してきました。
タワーマンションと低層マンションにはそれぞれメリットやデメリットがあり、自分がどこの優先順位を置くかによって選び方は変わってきます。
しかし、限られた時間の中ですべてを確認するのは簡単でないかもしれません。専門的な知識や情報が必要なものも多くあるので、不安があるようなら不動産のプロに相談しておいた方が安心です。
不動産会社の担当コーディネーターを上手く利用しながら、「買ってよかった」と思える物件を見つけていきましょう!
スケッチでは不動産のプロに個別相談ができ、さらにそれぞれの要望に合わせて優良な物件を紹介しています。
相談自体は何度でも無料なので、気軽に相談してみてください。
物件掲載サイトもご用意しておりますので是非ご覧ください!
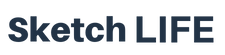














コメントを残す